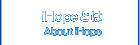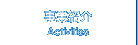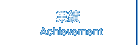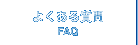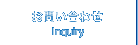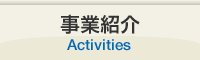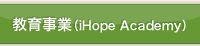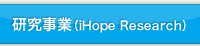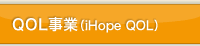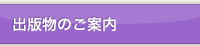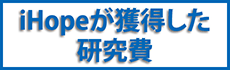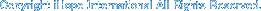疾患や診療の実態を記述する研究
医療は診断や治療によって支えられていますが、同時に、対象となる患者さんがどのぐらいの頻度で存在し、どのような医療を受けているかを明らかにすることも、たいへん重要です。そのためには、体に異常のない方も含めた多数の方々にご協力いただき、対象となる症状や通院・入院の状況、生活習慣、生活の状況等について調べる調査研究が行われます。
iHopeがこれまでに実施した研究は下記の通りです。
DOPPS・J-CLIP (Japanese Clinical Investigator's Publication support)
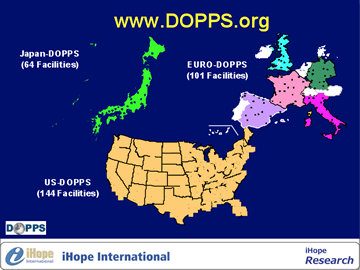 DOPPSは、世界の透析医療の診療実態の調査と診療の改善を目的とした、世界12カ国の国際共同研究です。透析を受けている患者さんの背景、治療内容、健康状態に関する詳細なデータを収集し分析します。
DOPPSは、世界の透析医療の診療実態の調査と診療の改善を目的とした、世界12カ国の国際共同研究です。透析を受けている患者さんの背景、治療内容、健康状態に関する詳細なデータを収集し分析します。
iHopeでは、2005年~2008年(第三期)の日本におけるデータ収集を担当しました。国内の透析施設から無作為に抽出された60施設の約2,300名の患者にご協力いただきました。
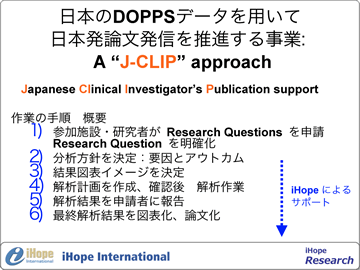 参加施設から得られた貴重なデータを解析し、参加施設、診療現場、社会に結果を還元することは、研究の負う社会的使命であると言えます。このような認識のもと、DOPPS参加施設よりリサーチ・クエスチョン(RQ)を公募して、論文化を推進する事業(J-CLIP)を行っています。これまでに、10編以上の英文論文が公表され、実際の診療に生かされています。
参加施設から得られた貴重なデータを解析し、参加施設、診療現場、社会に結果を還元することは、研究の負う社会的使命であると言えます。このような認識のもと、DOPPS参加施設よりリサーチ・クエスチョン(RQ)を公募して、論文化を推進する事業(J-CLIP)を行っています。これまでに、10編以上の英文論文が公表され、実際の診療に生かされています。
運動器臨床疫学研究
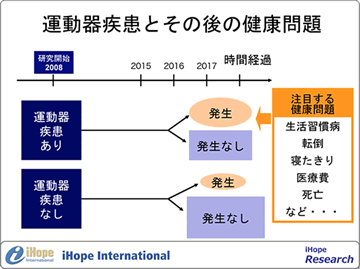 人口の高齢化に伴って、腰痛、膝痛、頚部痛等、運動器疾患(整形外科的な疾患)をもつ人の数が増えています。しかし、運動器疾患を持っていることが、日常生活やその後の健康状態にどの程度の不利益を与えるのか、分かっていません。
iHopeでは、福島県立医科大学、京都大学、順天堂大学、帝京大学などの研究機関と共同で、地方自治体の協力を得ながら、地域住民における運動器疾患による問題・その後の健康への影響について、長期的な調査研究を実施しています。
人口の高齢化に伴って、腰痛、膝痛、頚部痛等、運動器疾患(整形外科的な疾患)をもつ人の数が増えています。しかし、運動器疾患を持っていることが、日常生活やその後の健康状態にどの程度の不利益を与えるのか、分かっていません。
iHopeでは、福島県立医科大学、京都大学、順天堂大学、帝京大学などの研究機関と共同で、地方自治体の協力を得ながら、地域住民における運動器疾患による問題・その後の健康への影響について、長期的な調査研究を実施しています。
運動器疾患に関する全国調査
また、日本全国から無作為に選んだ数千名の方々にご協力いただき、頚部痛や脚の痺れがどの程度の方に発生し(有病割合調査)、生活がどの程度障害されているのか、また、それらの症状原因と考えられる要因は何かを調査しています。
上部消化管傷害の疫学研究
心血管疾患を発生した患者さんの再発予防には抗血小板薬が用いられます。実際の医療現場で、抗血小板薬がどのように用いられ、どの程度の人が意図したとおりに服薬を続けているかを調査しています。